「月島君ってほんとマイペースだよね〜」
もしかしたら
『もっと空気読めよ』って
言われてるのかもしれない。
だからといって僕ののろまな脳みそじゃ
面白い言葉で到底切り返せそうにないので、
「え、そうですか?」とだけ返す。
「うん、なんかご飯食べるときも人よりゆっくりだし、
突然ふらっとどっか行っちゃうしね。」
僕が話しているのはバイトの先輩の須々木さん。
彼女はとても気配り上手で仕事もできる。
現在大学四年生で大手食品会社への内定も決まっている。
バイトが終わり、まかないを二人で食べているときに
「ご飯を食べるのが遅い」なんて話を出すものだから、
僕はむきになっていつもより少し早くご飯を食べようとする。
けれど言い返したい気持ちがあるので
やっぱりそっちを優先する。
「…マイペースというか、ほかの人のペースに合わせる余裕がないんですよ。
最近人に言われて気づいたんですけど、僕って人と話しながら食べると、
しゃべってるときは箸が完全に止まっちゃうらしくて、
食事が中断してしまうんです。」
「あ〜確かにそうかも。
月島君今も手振りを交えて話してたからお箸が遊んでたもんねぇ〜。
…私ならそういう場合話し相手が話している間にガッと食べて、
相手が食事をしている間に場をつなぐために話をするかな。」
と話す須々木さんは既に完食している。
僕はそんな須々木さん(他の人も実践しているだろうが)のように器用じゃない。
相手を待たせつつ、けれども僕は話を続ける。
必要以上にあせり続ける。
一度に二つ以上の物事をするのが苦手だ。
この前路上で友人と自転車をこぎながら会話をしているとき、
自分が今ハマッている漫画のストーリーの説明を
どこからしようか考えていると、
正面の植え込みに衝突しそうになった。
といっても一つのことだけやっていても
集中しきれているわけではない。
とにかく何をするにも要領が悪い。
たいした特技もなく、
何かに対して努力家ってわけでもない。
他人から「マイペース」と言われる僕は、
結局他人のペースにも、自分のペースにも
あわせられていない。
誰のものでもないペース。
そんなペースに僕は勝手に振り回されている。

*
バイトからの帰り道。
夜中十時の川沿いのこの道にも慣れたけれど、
さすがに十月ともなると少し肌寒い。
等間隔についている街灯の前を
自転車で横切り続ける。
次の橋で曲がればもう
自分の住むアパートもすぐそこだ。
明日の講義は朝早い。
帰ってさっさと寝てしまおう。
人と会ってもうまく本音が話せない。
本当の自分のペースでいられるのは
自分の部屋くらいだろうか。
でもそこでは自分の気持ちを
吐き出すことはできない。
自分のペースで伝えられる場所がほしい。
自分のペースで伝えられる相手がほしい。
根暗なことを考えるなよ、と自分を戒め
前に向きなおった。
川沿いの見慣れない灯り。
それはある建物から漏れていた。
怪訝に思って僕はその建物に近づく。
居酒屋みたいな外観。
おでんのようなダシのいい香りが漂っている。
ただ店の名前はどこにも書かれていない。
―こんなお店あったかな…
お腹が空いている。
ただそのときの僕はそのことの不自然さに気づかなかった。
何故不自然か?
つい先程バイト先でまかないを腹いっぱい食べてきたからだ。
でも僕は確かにお腹が空いていた。
食べるものを欲していた。
気がつくと僕はその店(と思われる建物)の戸を開けていた。
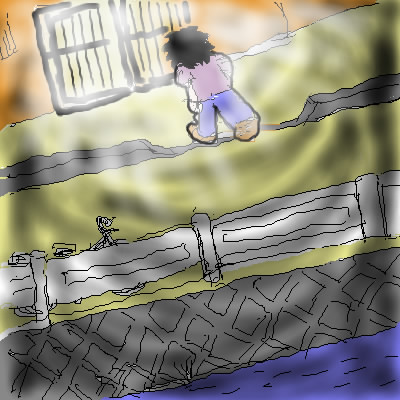
*
「へいらっしゃい」
戸を開けたと同時にしゃがれた男の人の声が聞こえた。
確かに飲食店のようだ。
最初に目に入ったのはカウンターごしの声の主だった。
あごひげのある角ばった精悍な顔立ち。
がっしりとした体格のおっちゃんだ。
「一名様で? こちらのカウンター席にどうぞ!」
言われるがままに席に着く。
見渡してみると座敷やテーブル席もある。
外で見るより少し広く感じるが、
いたって普通の居酒屋のように見える。
ただ、ほかのお客さんは見られない。
バイトと思われる
僕と同じくらいの歳の青年が
水を出してくれた。
「ご注文は?」
その質問に僕はあわてる。
お品書きを渡されず、突然聞かれた。
あたりを見回してもメニュー表がどこにも見られない。
「あ、メニューってあります?」
「ないです。」
「え?じゃあどうやって頼めばいいんですか?」
理不尽なバイト君の返答に僕が焦っている所に、
カウンター奥のおっちゃんが話しかけてくる。
「お客さん、この店に入ってくるときどんなにおいがしました?」
「え?えっと…おでんのにおい…だったと思います。」
「じゃあおでんだな!かしこまりました!」
といっておっちゃんは早速おでんの準備を始める。
居酒屋におでんというのも少し違和感を感じたが、
奥の調理場には確かにおでんの入ったダシ入れがあった。
ちょっと不思議な店だな、と思ったものの
そのときの僕はあまり深く考える余裕がなかった。
ただでさえバイト帰りなのに加えて腹ペコである。
いつもよりひどい疲労感が全身を襲う。
おでんのダシのにおいがする。
意識が朦朧がしてきた。
早くおでんをいただいて帰ろう…
早く食べたい…
あぁ明日の講義ってレポートなかったよな…
眠い…

「マスター、新しいお客さんだよ。」
この声で意識を取り戻した僕はドアのノブを持って立っていた。
僕の視線の先には…
リスを抱いた熊が座っていた。